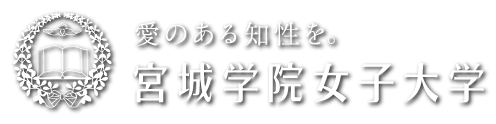皆さんはNHKで放送されていた「ブラタモリ」をご存じでしょうか。
この春、日本文学会では新入学生歓迎企画を開催することになりました。
「ブラタモリ」仙台編にガイドとして出演された木村浩二先生を講師にお迎えした特別企画です。
4月27日に全学科の学生を対象に講座「伊達政宗のまちづくりー城下町仙台のヒミツ」を、5月11日と18日の2回に分け、日本文学科の学生を対象にまち歩き「ブラキムラと辿る城下町のコンセキ」を実施しました。
ブラキムラこと木村浩二先生は、仙台の郡山遺跡の発掘調査や富沢遺跡保存館(地底の森ミュージアム)建設に従事されました。地底の森ミュージアム学芸室長を務めた後に、2017年3月まで仙台市教育委員会文化財課専門員を務められています。また、2024年3月まで宮城学院女子大学学芸員課程で授業も担当された学生に大人気の先生です。そして、まち歩きの達人でもあります。
先ずは4月27日(土)、「伊達政宗のまちづくりー城下町仙台のヒミツ」と題して木村先生にご講演頂きました(その時の記事はこちら)。
その後、木村先生の講座に出席した学生限定で実際にまち歩きを行うことに。
開催日の5月11日と18日は両日ともお天気に恵まれ、まさにまち歩き日和。
スタートは地下鉄東西線「国際センター駅」ですが、ここは仙台城二の丸跡地になります。出発前に木村先生から仙台城についてのお話を伺い、いよいよまち歩きに出発しました。ゴールは藤崎デパート周辺です。

スタートしてすぐ川のせせらぎが聞こえてきます。緑が生い茂ったところを覗くとそこには沢が。「千貫沢」と呼ばれる江戸時代からある沢で、二の丸の北側から広瀬川に流れ込みます。さらに歩くと二ノ丸登城口である「扇坂」が見えてきます。扇形に広がり広場のようになっていて、ここでお侍さんたちは草履を履き替えたり、袴を着替えたりしたそうです。
そこから石垣が続き、大手門があった場所へ。
木村先生から大手門を復元する計画があるという話を伺い、参加者からは歓声が上がりました。

大橋を渡り、いよいよ城下町へ。
大橋は仙台城と城下町を繋ぐ重要な橋ですが、かつて広瀬川にかかっていた大橋は、今の大橋よりももう少し上流にあったそうです。なんとその痕跡が今も広瀬川の川底に残っているそうで、木村先生はその一部に直接触れた経験がおありとか。
橋を渡り切ったところで一度休憩を挟み、水分をしっかり補給しました。

真っすぐ仙台駅方面に向かって伸びる大町通りを歩きます。大町は御用商人の町として栄え、大町四丁目には小間物商の「紅久」さんもありました。
奥州街道と大町通りの交差点には「芭蕉の辻」があります。「芭蕉の辻」は城下町の中心であり、大きなお店が立ち並ぶ大変賑やかな場所でした。木村先生より「芭蕉の辻」についてのお話を伺い、約2時間かけて堪能したまち歩きが終了となりました。

余談ですが、解散した後一部の参加者たちは藤崎デパートに足を運びます。
河岸段丘の名残が見られる場所ということで確認しておきたいですよね。しっかりと段差を確認し解散となりました。
講師の木村先生によるお話は大変面白く、参加した学生たちは熱心にメモを取り写真を撮影していました。取り囲むようにぴったりと先生にくっ付いて歩く様子は圧巻、相槌をうって一生懸命お話を伺う様子も印象的でした。
暑い一日に熱い企画を開催することができ本当に良かったと思っています。
日本文学会として初めて企画した「まち歩き」でしたが、ここまで学生たちに喜んでもらえるとは思わず大層嬉しかったです。
日本文学会では今後も学生参加型の企画を実施していきたいと思います。
それぞれ興味関心は異なるでしょうが、こういったイベントを実施することで、学生たちの好奇心を刺激できればいいなと願っております。