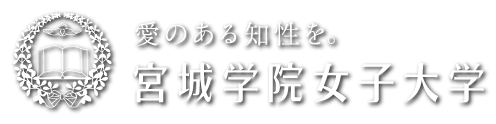日本文学科では毎年、日本が誇る伝統芸能を学ぶ「伝統文化教育プログラム」を実施しています。
2024年度伝統文化教育プログラム第一弾は、喜多流能楽師 佐藤寛泰 師による特別講義「能を学ぶ!」。5月29日に学内で実施しました。
第二弾は10月15日。人形浄瑠璃「文楽」を東京エレクトロンホール宮城で鑑賞しました。
第三弾は11月10日です。同じく東京エレクトロンホール宮城で「松竹大歌舞伎」の鑑賞をしております。
「文楽」「松竹大歌舞伎」ともにS席での鑑賞、チケットは日本文学科で用意し、「日本文化史」という授業で伝統芸能を学ぶ1年生が参加します。
そしてこの度、最後を締めくくる講座として、2月17日から18日にかけて喜多流能楽師による実技講座「能を体験する」を開催しました。
1年生から4年生まで、興味を持つ学生が参加しました。
今回教えていただいた演目は「半蔀」です。
『源氏物語』第4帖「夕顔」がベースとなる演目で、夕顔が光源氏との良い想い出を語ります。
この二人の恋愛は悲恋となるわけですが・・・・・・
「半蔀」では霊となった夕顔が現れ、光源氏を想いながらしっとりと美しく舞います。幻想的で儚げな雰囲気を醸し出すとても綺麗な作品です。
その「半蔀」に挑戦した日本文学科の学生たちはどうだったでしょう。
難しかったと思います。それでも皆、繰り返し練習しました。「夕顔」で光源氏が詠んだ和歌「寄りてこそそれかとも見めたそかれにほのぼの見つる花の夕顔」から始まるテキストに、たくさん書き込みしましたよね。2日目になると参加した学生たちの背筋は自然と伸び、美しい姿勢に。手もしっかりと伸び、舞扇を持つ指先も美しくなっていたと思います。声も出るようになりました。
謡いながら舞う。難しかったですね。
それでもとても素晴らしい経験になったと思います。もう少し学びたかったと思った方もいたのではないでしょうか。
喜多流能楽師の佐藤寛泰 師と鈴木敏彦先生、この度も大変貴重なお時間をありがとうございました。
心より感謝しております。
余談:ちなみにですが・・・・
「寄りてこそそれかとも見めたそかれにほのぼの見つる花の夕顔」という和歌は大河ドラマ「光る君へ」にも登場しましたよ~。