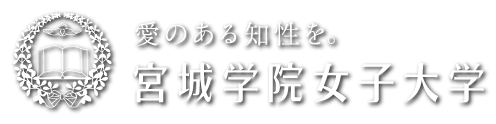私たちは7月7~10日の旅程で、沖縄における観光客誘致の現状を学ぶ現地調査を行ってきました。火災からの修復工事を終えようとしている首里城やユネスコ世界遺産にも登録されている斎場御嶽など多くの場所を巡って、観光の視点から地域の文化や歴史を学ぶ貴重な機会となりました。そんな中でも、特に心に残っているのが「ひめゆりの塔」の訪問です。
「ひめゆりの塔」は、1945 年の沖縄戦で亡くなった沖縄師範学校女子部・沖縄県立第一高等女学校の生徒や教師を慰霊するために建立された慰霊碑です。この塔は、戦争の悲惨さと平和の尊さを伝える象徴ともなっています。すぐ隣にある「ひめゆり平和祈念資料館」では、当時の学校生活の様子を記録した写真や資料、病院壕を再現したジオラマ、生存者の証言、遺品や手紙などが数多く展示されており、ひめゆり学徒隊として動員された少女たちが経験した過酷な現実に触れることができました。
展示を一つひとつ丁寧に見ていくうちに、彼女たちの人生が単なる歴史の一部ではなく、私たちと同じように日常を生きていた少女たちだったのだと、あらためて心に刻まれました。私はこれまで、戦争について深く学ぶ機会をあまりありませんでした。学校の授業で習っても、どこか自分とは遠い世界の話のように感じていたのかもしれません。ですが今回、自分よりも若くして命を落とした少女たちの存在に触れたとき、胸の奥からこみ上げてくる悲しみを抑えることができませんでした。戦争を知らない世代として、こうした場所で感じたことや学んだことを忘れずに、何らかの形で次の世代や誰かに伝えていくことが、私たちにもできる小さな責任かもしれないと感じました。
また様々な場所を調査する中で現地の方とお話する機会がありました。その際に「どこに行ったの?」と聞かれ「ひめゆりの塔に行きました」と答えると、「あなたたちのような若い人が観光の一環で訪れるのは珍しい。」との声を聞くことができました。その言葉がとても印象に残っています。たしかに、観光で沖縄を訪れる同世代の多くは、美しい海やリゾートを目的にしていて、戦争に関する史跡を訪れる機会は少ないのかもしれません。けれども、ひめゆりの塔や資料館は、ただ「悲しい場所」ではなく、過去を知り、そしてこれからの自分の生き方を考える大切な場所だと思います。だからこそ、観光という枠の中でも、こうした学びのある場所に足を運ぶ人がもっと増えてほしいと考えました。
今回の沖縄調査で、ひめゆりの塔を訪れたことは特に心に残る体験となりました。戦争の悲惨さや平和の大切さを実感し、こうした場所を訪れることの意味を強く感じました。そして、今回の私たちの体験や気づきをまとめたこの記事が、誰かにとって「行ってみよう」と思うきっかけになれば嬉しいです。
(現代ビジネス学科3年 三浦笑加)