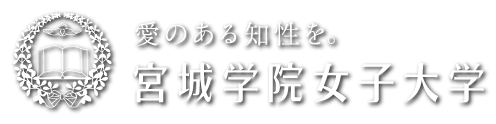7月28日(月)の5校時に、家庭裁判所調査官の講演会を行いました。家庭裁判所調査官は、心理学を活用できる専門職(国家公務員)の一つです。
講師には、松本祐里氏(仙台家庭裁判所 主任家庭裁判所調査官)をお招きして、「家庭裁判所における調査官の役割」についてお話しいただきました。
ご講演では、家庭裁判所が少年事件、家事事件を扱う裁判所であること、また、これらの事件において家庭裁判所調査官がどのような役割を果たすのかについてお話を伺いました。2種類の模擬事例を用いたワークを通して、調査官が個々の事例の記録・資料等のどこに着目し、どのような調査をするのかを考えながら、体験的にお話を伺うことができました。
当日は本学科2~3年生、約30名が参加しました。ご講演後の質疑応答も活発で、学生達の質問を通して、家裁調査官の仕事についてさらに深く学ぶことができました。
なお、今回参加した学生の一部は、9月に現場部の活動で、家庭裁判所を訪問します。本講座の感想からは、訪問予定の学生達の参加意欲が高まり、さらに知りたいことが出てきたことがわかりました。


参加した学生たちの感想の一部を以下にご紹介します。
- 「家庭に平和を、少年に希望を」という言葉が印象に残った。まさに、調査官がどのような仕事であるかを表しているようで、様々な視点から調査をし、非行少年には再非行を防ぐために、家事事件では当事者が納得できるように、働きかけている調査官という仕事の理解に繋がった。
- 模擬事例として示されたスライド1枚分の情報だけからでも、疑問は数多く出てきて、実際の調査の難しさの一端を知ることができた。
- 今回の民法改正(共同親権)でも仕事に影響があるとうかがい、職に就いてからも学び続ける姿勢が大事になることがわかった。
- 家庭裁判所に関わる機会はこれまでなかったが、家族に関する内容の裁判なので、身近に考えやすかった。とても尊敬できるお仕事の1つになると感じた。
- 心理学が現場でどう生かされるのかを知ることができた。今学んでいるカウンセリングが、この仕事に直接活かされていることを知り、関心が強くなった。
学科では、後期も卒業後の進路選択に役立つ企画を行っていきますので、ぜひ参加してください。
(木野記)