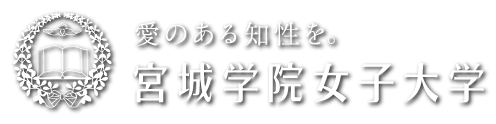7月14日(月)の5校時に、「言語聴覚士」講演会を行いました。
言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist:ST)とは、言葉によるコミュニケーションに困難などがある方に対して、機能の維持向上を図るための援助を行う専門職です。
今回の説明会では、STである鈴木將太先生(仙台青葉学院短期大学)と、本学OGである鈴木珠緒さん(2022年度心理行動科学科卒業生・仙台青葉学院短期大学 言語聴覚学科3年次在学中)に、次のようなお話をうかがいました。
鈴木將太先生によるお話
(ST・仙台青葉学院短期大学 言語聴覚学科)
人のコミュニケーション過程、援助の対象となる障害、STの活躍の場、国家試験について説明していただきました。
STが援助を行う対象は、「首から上のこと」と考えるとよいとのことでした。つまり、話すこと、聞くこと、思考すること、食べることなどの障害が援助の対象となります。また、「失語症を想像することは難しいが、自分がなじみのない国に行った状態を想像すると、少し理解に近づくことができる。」というお話もありました。
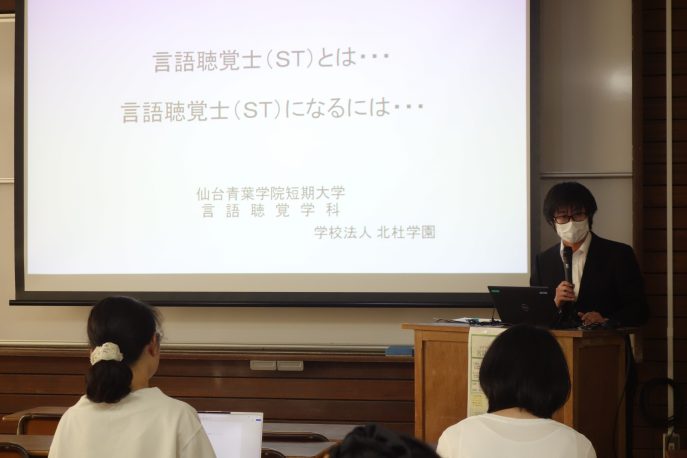
鈴木珠緒さんによるお話
(2022年度心理行動科学科卒業生・仙台青葉学院短期大学 言語聴覚学科2年次在学中)
卒
宮城学院女子大学在学中に参加した言語聴覚士説明会が、STを志望するきっかけになったとのことです。現在は、3年次の実習を終え、国家試験に向かって勉強しているとのことです。将来についても、どんなSTになりたいか、どの年齢やどの症状の方を対象に支援したいかなど、お話いただきました。

その後の質疑では、STの実習における治療プログラムの話、患者さんの症状や年代、急性期から生活期までのおよその治療経過などが話題になりました。
講演には本学の学生13名が参加しました。
講演後には参加者から次のような感想が聞かれました。
・STが声やことばの機能の障害のほか、聞こえの障害や発達の遅れ、食べ物の飲み込みの障害など、様々な障害に対応しなければならないという、幅広い専門知識を求められる職業であることがわかりました。
・私は手話に興味があるのですが、STの話を聞けてよかったです。進学する進路も考えたいなと思いました。
・「他の様々な専門職の方々とチームになって、人の人らしさを支えるために働く」という点に非常に魅力を感じました。
心理行動科学科の卒業生が仙台青葉学院短期大学に進学しているというご縁もあって、この講演会を毎年開催しています。
今年度の講演会も、将来を発見し、進路を見直す機会になったようです。
(瀧澤記)