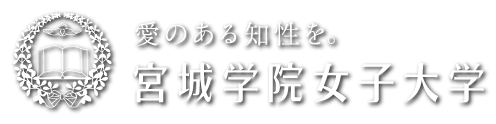7月9日(水)、「音楽科教育法III」(音楽科3年生対象・教職必修科目/担当 水口 俊彦先生)の授業の一環として、ワークショップ「グローバル音楽文化講座」を開催しました。

絵本「スーホの白い馬」(福音館書店)を読んだことのある方は多いと思います。この本の中で描かれている「馬頭琴」という楽器について、この楽器が生まれた国はどんな国なのか、どんな音色がする楽器なのか、想像したことはありますか?
講師の荒井 俊子先生は、教員時代、世界中を旅して、その土地に深く根差し、生活の中で育まれてきた多くの楽器と出会い、その素朴な音色に魅了されたそうです。身近な材料を使って、様々な工夫が施された楽器は、普段、私たちが慣れ親しみ、イメージしている「楽器」とは異なる価値観と魅力を持っています。

学生たちの目の前には、荒井先生ご自身が各国を旅して収集し、教員時代に教材として活用してこられた楽器がたくさん並べられました。学生たちは実際に楽器に触れながら、音を出してみたり、装飾の技術を観察したりして、感想を発表しあいました。


竹や木の実、サボテンなど、身近な植物を使った楽器、動物の毛や皮を材料としてつくられた楽器など、珍しい楽器も多く、それらの楽器がどのような風土の中で生まれ、使われているのか、先生のお話は尽きることがなく、学生も興味深い様子で、説明を聞いていました。

実際に触れる機会の少ない楽器に触れ、世界の音楽文化について視野を広げることができました。
荒井先生、ありがとうございました。