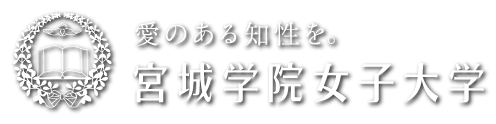日本国憲法の基本原理の1つとして個人の尊重がある。実際、憲法13条には次のように規定されている。
すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
この規定は、いわゆる幸福追求権を保障するものであり、日本国憲法の授業では1コマ分の時間を使って学習する。この権利の内容には自己決定権が含まれ、そのなかに、論者によって見解は分かれるが、婚姻に関する自己決定がある。
日本国憲法上、婚姻については、家族に関して「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」原理に則した制度設計の要請・指針を規定していると一般に解される24条や、性別による差別を禁止する法の下の平等を規定する14条も関連していると考えられる。
憲法24条1項では、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と規定されている。この「両性」という文言が使われていることから、婚姻は異性間のみのものであるという見解もある。しかし、現在では、この婚姻のなかには同性間の保障も含まれるという主張も有力とされている。
周知の通り、現在の日本では同性間の婚姻は認められておらず、同性パートナーシップ制度が認められている。したがって、同性パートナーとの婚姻を望む個人にとっては、その彼/彼女らの婚姻の自己決定を実現することができない状況である。
このような状況を是正するために、すなわち、同性婚が日本において認められることを求めて、全国の5つの地裁で「婚姻の自由をすべての人に」訴訟が提起され、6件の地裁判断がすでに下されている[1]。高裁では、札幌、東京、福岡、そして先日(2025年3月7日)に名古屋で、同性婚を認めない現行法などは憲法に違反しているという違憲の判断が出された。さらに、3月25日には、大阪高裁の判決が言い渡される(本稿執筆は2025年3月15日)。
先日の名古屋高裁では、「同性カップルが法律婚制度を利用できないと区別しているのは、個人の尊厳の要請に照らして合理的な根拠を欠き、性的指向によって差別する取り扱いだ」などとして、法の下の平等を定めた憲法14条1項と、家庭内の個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項に違反すると判断した[2]。
ここで私見を少し述べると、「婚姻の自由をすべての人に」訴訟の他の高裁判決にも言えることだが、裁判所は婚姻について、個人の人格的利益を重視しつつあると思われる。つまり、婚姻についての自己決定が少しずつであるが、尊重されてきているように感じられる。たしかに、婚姻についての人々の考えはさまざまであろう。たとえば、婚姻を従来通りの異性間のみであると思う人もいれば、反対に、現行の婚姻制度のなかに同性婚も含めるべきだと思う人もいるだろう。
しかし、同性婚に関して重要なことは、異性婚を望む者たちには、法律婚制度の利用(ここでの意味では、自己の婚姻についての自己決定権)が認められるのに対して、同性婚を望む者たちには、その制度の利用や婚姻についての法的権利が制限されるべきではない、ということではないか。
筆者は、先日、『ジェンダーの視点で学ぶ憲法入門』(大月書店、2025年)を刊行させていただいた。本書は、各章で日本国憲法の解説とジェンダー法に関する説明の二部構成からなる。本書なかで、憲法上の幸福追求権のより詳しい説明や、上記の名古屋高裁判決以前の「婚姻の自由をすべての人に」訴訟のいくつかの判決について取り上げている。少しでも興味を持たれた方は是非、一読していただければ幸いである。(憲法、ジェンダー法・川口 かしみ)
[1] 以下、同訴訟に関しては公益社団法人Marriage For All Japan ――結婚の自由をすべての人にホームページ「裁判情報」https://www.marriageforall.jp/plan/lawsuit/(最終閲覧:2025年3月15日)参照。
[2] NHKホームページ「同性婚認めないのは憲法違反 名古屋高裁2審の違憲判断は4件目」/www3.nhk.or.jp/news/html/20250307/k10014742371000.html (最終閲覧:2025年3月15日)など参照。