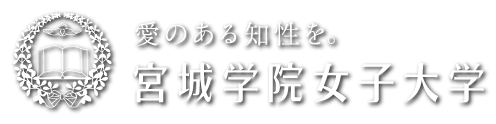7月26日(土)、宮城県美術館の濱﨑礼二副館長をお招きし、学芸員課程シンポジウムを開催しました。
第一部の濱﨑氏 基調講演は、宮城県美術館の収蔵作品である長谷川潾二郎 作《猫》にまつわる話からスタートしました。
会場内には額に入れられた《猫》がイーゼルに立てかけられ、濱﨑氏の「どうぞ近くでご覧ください」という声掛けから受講生たちはじっくりと間近で鑑賞をし、思い思いの感想を持参のノートに書き留めていました。

絵画などの美術品は温度や湿度、光に敏感です。収蔵庫内だけでなく展示室はもちろん、他の施設での展覧会等のため外へ持ち出す際の移動中も、常に適切な温度調整や光量の調節がなされています。
美術品の展示にあたり適切な調整のされていない会場内に本物の美術作品をそのまま飾ることは、本来であれば考えられないことです。
「では今回この《猫》をどうやって持ってきたのか?」という濱﨑氏の問いかけに、受講生たちは頭を悩ませながら回答していました。
なぜ、この作品を教室内で鑑賞することができるのでしょうか。その答えは、この日濱﨑氏が持ってきた作品がとても精巧な「レプリカ」であるからです。この事実を明かされた受講生たちはとても驚いた様子でした。
講演中は濱﨑氏が受講生に問いかけるシーンが度々見られました。自分の考えや感じたことをメモにとることで、話を聞くだけではなく、共に考えるという有意義な時間となりました。
作品がレプリカであると知る前と知った後での印象の変化を踏まえ、第二部へと進みます。

第二部では学芸員課程で博物館実習を履修中の実習生3名がパネリストとなり、レプリカ展示の意義について濱﨑氏と議論を行いました。
それぞれお互いの意見に耳を傾けつつ、これまでの自身の経験から作品が「本物であること」の意味、「レプリカであること」の意味を考え意見を発表しました。
「本物」の作品には如何なる魅力や価値があるのか?なぜ美術館や博物館ではレプリカを展示することがあるのか?その意義、役割は?
普段から来場客として美術館へ足を運び、さらに学芸員資格の取得を目指す受講生たちにとって大変興味深い意見交換の場となりました。

最後に濱﨑氏から宮城県美術館についてのお話をうかがいました。
現在休館中の宮城県美術館で行われている事業やイベントについて説明いただき、展示場所が無い中で美術体験を届けるためどのような工夫を凝らしているのか、貴重な裏側をお聞きすることが出来ました。
再開館後はまた新たな美術体験の提供をお考えとのことです。開館がさらに楽しみになるお話でした。
本シンポジウムの司会進行は人間文化学科 菅野洋人教授、ポスターの作成や設営・受付等は学芸員課程の実習生が担当しました。