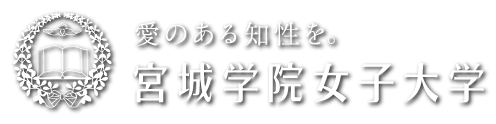人間文化学会主催、MGUジェンダー教育研究センター共催で、2025年11月11日の昼休みに、C306教室で、「教育と尊厳―ロヒンギャ女性の人権とエンパワーメントー」というテーマの講演会をオンラインで開催しました。講師は、NGO団体であるプラン・インターナショナル・ジャパン・プログラム部の内海摩耶氏です。
内海氏は、自分がNGO団体に勤めるようになったキャリアの話から講演をはじめ、バングラデシュにおけるロヒンギャ難民の生活の実態、劣悪な生活環境などについて、スライドをもちいて、わかりやすくお話をされました。とくに、女性の教育が低いこと、教育を受けられないために就職につながらないこと、妊娠・出産の死亡率が高いこと、女性への暴力など、女性をとりまく過酷な状況について、お話をされたので、参加した50名ほどの学生たちは息をのむようにきいていました。また、それに対するプラン・ジャパンの支援について具体的に紹介され、成果があがっていることがわかりました。学生の感想をいくつか紹介します。
「ロヒンギャ難民という名前だけ知っていましたが、国籍や市民権が認められていないため正確な人数さえわからない、居場所さえない、帰るところがない、必要な支援を受けられないという話をきいて、ここまで状況が深刻であることは知らず、驚きました。」『難民になれない難民』という言葉のインパクトがとても強烈でした。難民認定されないことで、労働が禁止され、教育を受けられない状況にあることを初めて知りました。」
「ロヒンギャ難民の女性は初潮が始まると自由に外出できず、18歳になるまでに8割が妊娠・出産をしていて、自分だったら、とても耐えられない生活だと思いました。」
「教育を十分に受けることができず、読み書きが困難であることはある程度は想像がついていましたが、男女格差があらわれた数値を見ると、女性に対する教育阻害がみられ、その背景に、児童婚や持参金などジェンダーの問題が深く関わっていることがよくわかりました。」
「先進国では多くの人が幸せになりたいから結婚をしますが、途上個の場合は結婚が女性の未来を奪うこともあるのだと胸が痛む思いでした。」
「スライドの写真の前半は、暗い表情の子どもたちばかりでしたが、後半になると、プランの教育支援を受けて勉強をしている子どもたちの表情がとても明るく、プランのプロジェクトがどれだけ嬉しいものであるのか伝わってきました。」
「国籍や学べる環境が当たり前にあたえられていることを普通だと思わず、今の環境に感謝し、自分ができる国際支援に取り組んでいきたいと思います。」