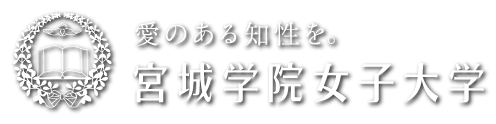9月9日(火)10日(水)、人間文化学科高橋ゼミ(日本史)が東京へのゼミ旅行を行いました。近世・近代の人の移動や交流・物流に関する学びを深めることを目的にした旅行です。
江戸時代に東海道の起点だった日本橋からスタートし、まず松尾芭蕉関連の施設として江東区芭蕉記念館と芭蕉庵跡を訪れ、江戸時代に仙台藩の物資が運ばれた仙台堀川沿いを歩きました。また、江戸時代から名所であった浅草寺と、浅草寺を管理する別当であった寛永寺を参詣しました。昼夜を問わず外国人旅行者であふれる浅草寺は、今日の国内観光地の現状を知る機会にもなりました。
 江東区芭蕉記念館
江東区芭蕉記念館
 芭蕉庵跡
芭蕉庵跡
 仙台堀川
仙台堀川
 浅草寺
浅草寺
このほか、郵政博物館では近代の交通・郵便関係の展示を見学すると共に、日本郵便オリジナルキャラクター「ぽすくま」を作るワークショップを体験しました。上野では、世界遺産である国立西洋美術館の外観を見物し、国立博物館では特別展「江戸 大奥」を鑑賞しています。
 郵政博物館
郵政博物館
-687x515.jpg) ワークショップ (もこもこモールでくま作り)
ワークショップ (もこもこモールでくま作り)
 寛永寺
寛永寺
 国立博物館 (特別展「江戸 大奥」)
国立博物館 (特別展「江戸 大奥」)
2日間、30度超の暑さの中で盛りだくさんのスケジュールをこなしましたが、全員元気に過ごすことができました。現地で実物を目にすることで、過去を追体験できたのではないでしょうか。
以下に参加者の感想を紹介します。
芭蕉記念館に行った際に、蕉門十哲という存在を初めて知ったと共に、奥の細道で知られる河合曾良が十哲に入っていないことに驚きました。また、浅草寺の仲見世にある店の創業がどれも明治以降であると気付きました。江戸時代の仲見世は寺院の集まりであった歴史を間接的に伝えているように思えました。(4年 木村灯里)
一日目は日本橋、芭蕉記念館、仙台堀川の見学に行きました。芭蕉記念館では、松尾芭蕉由来の資料展示や、芭蕉が旅人として俳句を詠んだ歴史に触れることができました。仙台堀川の名の由来には、仙台藩からの物資の流通があったことがわかり、現在でも仙台の名が引き継がれていることに面白さを感じました。二日目は浅草寺・寛永寺参拝、郵政博物館・東京国立博物館見学を行い、どちらも歴史を目の当たりし、充実した東京観光となりました。神社参詣や博物館には世界各国から観光客が集まり、実物に触れることの非日常体験が可能です。このような観光スポットを、ゼミの学習の一環として歴史に触れ、学びを総括できたことは、今後においても心に残る経験となりました。(4年 佐藤ひより)
ゼミ旅行では、事前に学んでいた浅草寺と寛永寺の関係を実際に確かめられたのが印象的であった。浅草寺が江戸時代に寛永寺の支配下にあったことは事前学習を通して理解していたが、現地を訪れることでその事実がより身近に感じられた。特に、当時の寛永寺が国立博物館や西洋美術館の辺りまで広がっていたと知り、現在の規模との違いに驚かされた。当時の寛永寺がどれほど大きな力を持っていたのかを現地を歩きながら実感できたことは、とても貴重な経験となった。また、寛永寺の門を潜った瞬間に風が吹き、木々が揺れる光景を目にし、不思議な気持ちになると同時に、より一層歴史的な空間に包まれたように感じた。(4年 鈴木咲良)
博物館の展示が印象に残りました。国立博物館の大奥展では華やかで貴重な展示を間近で見学することができました。郵政博物館では郵便の歴史を辿り、実際に使われていた道具から当時の雰囲気を感じられ、感慨深かったです。新たな学びにつながり、充実したゼミ旅行となりました。(4年 大黒恵)
日本橋や浅草、深川、上野を巡り、江戸の歴史や文化を肌で感じることができました。芭蕉記念館や大奥の展示では、当時の暮らしや社会の仕組みに圧倒され、歩き回ることで当時の街の雰囲気も体感でき、充実したゼミ旅行でした。(4年 都甲倖乃)
国立博物館の大奥展が印象に残りました。大奥について詳しくは知らなかったけれど、想像以上に面白かったです。華やかな衣装や実際に使われていた道具、当時の生活の習慣を知ることができ、歴史の世界に少し入り込めた気がしました。貴重な体験でした。(3年 相澤彩花)
1番印象に残ったのは国立博物館の江戸大奥展です。展示にあった当時の火災のときに使われていた服装が現代の防災頭巾に似ていて驚いたため印象に残っています。2日間で日本文化や歴史にたくさん触れることができ貴重な体験をすることが出来ました。(3年 鹿野悠心)
江東区芭蕉記念館では、松尾芭蕉が日本橋に来た理由が気になったり、また郵政博物館では以前の郵便箱は黒色でトイレと間違えられ用を足す人もいて問題になっていたことなど、疑問に思った点やはじめて知ることが多くありました。江戸大奥の特別展も行く機会がなかったので今回のゼミ旅行に参加して行くことができ良かったです。(3年 上川原怜那)
ゼミ旅行を通して、一番印象に残った場所は「仙台堀川」です。仙台堀川を通して、仙台藩で生産された米などが運ばれていたことを学びました。また、仙台藩産の米が江戸におけるシェア率が高かったことは、とても興味深く感じました。現在、宮城が米どころになっている基盤は、江戸時代にまで遡ると考えました。(3年 佐藤智葉)
(文責 人間文化学科・高橋陽一)