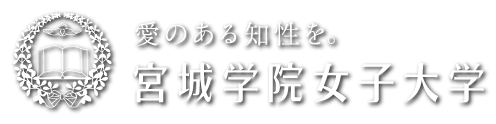本報告は、人間文化学科で、2024年12月に2週間にわたり実施されたフィールド実習(インド)の記録PART2です。
実習担当教員 八木祐子
3.世界遺産見学
12月23日の昼の飛行機で、ベナレスからデリーに向かい、バスで約6時間近くかけて、アグラに移動した。24日の午前中に、世界遺産であるアグラ城とタージ・マハルを見学した。学生たちは、ムガル時代の壮麗な建築とインド人観光客の多さに圧倒されていた。昼食後、バスでジャイプールへ6時間かけて移動した。ジャイプールは、ラジャスターン州の州都であり、かつてマハラジャ(藩王)が統治した街として知られている。25日の午前中は、シティ・パレスや天文台などを巡り、マハラジャのつくった街のきらびやかさと、イスラム教とヒンドゥー教の2つが混交した美しさを堪能した。昼食後、風の宮殿や旧市街でのバザール見学とショッピングを楽しんだ。
26日は、マハラジャ気分で、象に乗って、世界遺産のアンベール城を観光し、ジャイプールの名産であるハンド・プリントの作業工程の見学をおこなった。ショッピング・モールで昼食後、旧市街のバザールを見学し、夜は地元の民俗舞踊をみながら夕食をとり、最後には一緒に民俗舞踊を踊って楽しんだ。27日の朝からバスで6時間かけてジャイプールからデリーに移動した。夕方に雨が降ったので、ホテルでグループごとに、アンケートの整理やまとめをおこなった。28日は、お土産屋で買い物をしたあと、夕方の飛行機でデリーを飛び立った。29日朝に羽田に到着し、昼頃、仙台に、無事、帰着した。



4.実習のグループ活動内容
今回、調査実習をおこなったベナレス(Benares)は、ヒンドゥー教の聖地として有名な宗教都市である。数千年の歴史をもち、世界中から観光客が訪れる観光都市であるともに、人口160万をこえるウッタル・プラデーシュ州東部の政治・経済の中心地である。ベナレスは、古代ではカーシー(Kashi)と呼ばれ、イギリス植民地統治時代にはバナーラス(Banaras)、近代以降はワーラーナスィー、ヴァラナシ(Varanasi)と呼ばれるなど、呼び名や表記の方法が異なる。ベナレスは、日本人特有の呼び方である。
学生たちは、BHUのなかにあるヴィシュワナート寺院の中庭や大学構内、またヒンドゥー教寺院、ガート(沐浴場)、ショッピング・モールなどでアンケート調査やインタビューをおこなった。調査対象者は、学生だけでなく、観光や巡礼にやってきた人々、ベナレスに暮らす市民など様々で、年齢層も10代~70代まで多岐にわたる。チューターさんが熱心に手伝ってくれ、各グループとも約100名の方々にアンケートをおこなうことができた。調査実習中は、毎晩、リーダー・ミーティングをおこない、グループごとに、その日の活動報告と翌日の活動予定について報告をおこない、引率教員がコメントをした。
各グループのテーマと内容を簡単に紹介する。3年生1人、2年生1人、1年生2人で構成されたAグループは、「インド人の信仰観、死生観」をテーマとして、2004、2012、2016年の調査と比較して、主にヒンドゥー教徒の信仰に対する考え方や聖なるガンジス河に対する思いへの変化について検証した。
3年生2人、2年生1人、1年生2人のBグループは「インド人の美、化粧」をテーマに、調査をおこなった。メイクや美への考え方について調査し、サロンを訪問するなどのフィールド・ワークもおこなったことで、インド女性が自然な化粧を好み、インナー・ビューティーを大切にすることをあらためて認識した。4年生2人、3年生1人、2年生1人、1年生1人のCループのテーマは「インド人の食文化、デリバリー」で、2012、2016年の調査報告と比較することで、コロナ禍を経て、食に対する意識やデリバリーに対する需要がどう変化したかを調査した。帰国後、インド実習中間報告会をおこない、各グループがアンケート調査やインタビューの内容を報告した。現在、アンケート調査やインタビューをまとめ、考察を加えた『2024年度インド実習報告書』を作成中であり、各グループの成果に期待したい。
実習をつうじて、学生たちは同世代のチューターさんや現地の人とふれあい、貴重な経験をすることができ、インドの社会や文化についての理解が深まったと思われる。日を追うごとに、チューターさんに頼らず、自分で英語を使ってアンケートをおこなうように頑張ったり、地元の人たちとコミュニケーションをとるようになったりと、学生たちの成長を実感できた。1年生から4年生までの学生が参加した実習だったが、だんだんと仲良くなり、互いに協力しあって実習をすすめる様子がみられた。帰国後、「インドにまた戻りたい」「ベナレスに留学したい」という学生たちも多く、かなり充実した実習になったと思う。
引率に同行してくれた杉井信先生の的確なサポート、国際交流基金の日本文化センターの鈴木千晶さん、澤木翔さん、日本語講座受講の学生のみなさん、BHUの日本語学科のアナンタ・プラサード先生の多大なご協力、チューターをつとめてくれたBHU学生のみなさんの真摯な取り組み、また、ガイドのパリック・ショービー氏をはじめ、友人のミントウ・マノージ氏、休みをとって駆け付けてくれた卒業生2人などのおかげで、実習がスムーズにすすんだ。あらためて感謝を申し上げたい。学生たちには実習の体験を生かして、さらに異文化理解をすすめてほしいと願っている。


「インド実習に参加して」 4年 山下怜奈
インド実習では、目で見て、体験して、心から感じることが本当にたくさんあった。特に印象的だったのはガンジス川だ。沐浴をする人々、祈りを捧げる巡礼者、祭りのような宗教儀式、さらには火葬場の光景までもが広がるこの川は、生きる人にとっても、亡くなった人にとっても、人々が思いを馳せる神聖な場所であった。一方で、川の遠くからバイクのクラクションが聞こえ、観光船が行き交い、物売りが盛んに声をかけてくる。神聖でありながらも混沌としたその空間は、まさに「清濁併せ呑む」ガンジス川そのものだった。雑多で、エネルギーに満ちた風景がとにかく面白かった。
街も賑やかだった。市民の足、オート力車での移動が多かったが、牛がその辺を闊歩していたり、信号待ちをするラクダを見かけたりすることもあった。朝から夜まで活気づく街の様子に、インドの活力を感じた。見渡す限りすべてが私たちに新鮮に映り、歩くだけでも楽しかった。
この実習の一番の目玉は現地の学生との活動だった。BHUの学生たちと一緒に、ニュー・ヴィシュワナート寺院の前でアンケート調査を行った。現地の人々と直接話し、学生だけでなく、近所に住む人、旅行中の家族など、さまざまな人と交流できた。驚いたのはインドの人々のフレンドリーさだ。声をかけるとほとんどの人が笑顔で応じてくれ、お互いのことを話したり、一緒に写真を撮ったりした。印象的だったのは、「家族全員で写真を撮りたい」と言われて承諾したところ、なんと20人ほどに囲まれた場面だ。その家族は親戚一同でヴァラナシを訪れていたらしい。このようなエピソードからも、インドの価値観や文化を垣間見ることができた。
ヴァラナシでの4日間の活動は本当に濃密な時間だった。BHUの学生たちには本当に親切にしてもらい、彼らと過ごす中で、インドの文化や学生生活について多くのことを知ることができた。ヴァラナシ滞在最後の夜にはパーティーを行い、大いに盛り上がった。思い出に残そうと写真撮影タイムは終わらず、別れが本当に名残惜しかった。テスト期間にもかかわらず、たくさんのサポートをしてくれたBHUの学生には心から感謝している。
大学生活の最後にこのインド実習に参加できたことを本当に幸運だと思う。ひとりで訪れても経験できないようなディープな体験ができた。学生のうちにインドを訪れ、自分の目で見て、頭で考え、肌で感じられた経験は本当に貴重で、これからの人生にも活きてくるだろう。また必ずインドを訪れたい。スパイスたっぷりのアツアツのチャイを飲みながら、ガンジス川の日の出を眺める日を心待ちにしている。
最後になるが、この貴重なインド実習に私たち学生14人を連れて行ってくださった八木先生、学生の学びや健康を第一にたくさんのサポートをしてくださった杉井先生に、心から感謝している。また、現地での13日間、私たちをさまざまな場所に案内し、多くのことを教えてくださり、学生のケアもしてくださったガイドのショービーさんにもお礼を申し上げたい。この実習に関わってくださったすべての皆さんに感謝し、この文章を締めくくる。
インド実習は、私たちを大きく成長させ、人生においても忘れられない学びを与えてくれました。ありがとうございました。